

 8月27日(月)には、今年度最後の魚津地区教育センター協業講演会が開催されました。第三回は「道徳に関する講演会」として、京都産業大学 教授 柴原 弘志先生をお招きして、「道徳科の学習指導・評価の在り方」についてご教示いただきました。
8月27日(月)には、今年度最後の魚津地区教育センター協業講演会が開催されました。第三回は「道徳に関する講演会」として、京都産業大学 教授 柴原 弘志先生をお招きして、「道徳科の学習指導・評価の在り方」についてご教示いただきました。
柴原氏は、学習指導において大切にしなければいけないこととして、「自己内対話」であるとおっしゃりました。道徳的価値や人間としての生き方を深めるためには、「自分が自分に自分を問う」時間を保障することが大切であると学びました。
また、評価の面では、「評価の視点」と「評価の観点」を明確にし、その視点から教師の授業観察、ノート、発言などを基に、観点に沿って継続的に捉えること。そして、授業者自身も学習指導過程や指導方法に関する評価を行っていくことで、「深く考え、議論する道徳の授業」への転換を図ることができる。
柴原先生のパワフルな熱い講演。これは、それだけ道徳科の授業改善を早急に図って欲しいという切なる願いにも感じられました。柴原先生にいただいたヒントを基に、2学期の授業改善を積極的にいっていきましょう。
投稿者「朝日町教育センター」のアーカイブ
8月27日 魚津地区教育センター協業講演会「道徳講演会」
8月24日 小中高教育講演会と情報交換会



 8月24日(金)には、小中高教育講演会と情報交換会が開催されました。この会は、毎年、夏季休業中に開かれており、朝日町内の小中高校の先生方の資質能力の向上を図るとともに、未来を担う大切な子供たちを共通理解のもとに、町全体で育てていくという目的をもっています。
8月24日(金)には、小中高教育講演会と情報交換会が開催されました。この会は、毎年、夏季休業中に開かれており、朝日町内の小中高校の先生方の資質能力の向上を図るとともに、未来を担う大切な子供たちを共通理解のもとに、町全体で育てていくという目的をもっています。
今年度は、魚津市にある「株式会社 アイティオ」 代表取締役社長 伊東 潤一郎氏をお招きして、「中小企業のものづくりと人材育成」と題してご講演いただきました。
伊東氏は、会社の金型作りにおいて常に失敗を恐れずに新しいものに挑戦する姿勢(人工衛星や携帯電話や、人を幸せにする製造業の喜び、企業と教育の人材育成に対する共通点等について、写真や実例を交えてお話しいただきました。
伊東氏は、生きていくために必要な力を「人間力・体力・学力」であるとおっしゃっておられました。まさに、学校教育の場でこの基礎を養っていかねばなりません。町内の小中高、そして社会全体で最も必要とされる(人罪→人在→人材ではなく)→「人財」を育成するために協力していくことが、未来の朝日町、未来の日本、未来の世界のために必要であることを感じた1日でした。伊東社長 ありがとうございました。
8月24日 学校教育運営研修会 「海中の宮殿 鹿嶋神社」



 8月24日には、「朝日町学校教育運営研修会」が開催されました。
8月24日には、「朝日町学校教育運営研修会」が開催されました。
講師には、鹿嶋神社 宮司 九里 文子氏をお招きし、「古代玉作の里に甦る神度神社」と題して境内にてご講演をいただきました。
九里様のお話は、「鹿嶋神社にまつわる海中洞窟の宮・竜宮の神話」、「明神と記された絵図や地内から出土した勾玉からの新たな発見」、「北村喜代松の最高傑作と言われる一木造りによる素掘り彫刻」等、驚きの事実や想像が膨らむ興味深いものばかりでした。その語られる姿から、「鹿嶋神社の歴史・文化の伝承」への意欲を強く感じ、積極的な研究・広報活動に努めておられることに感銘を受けた教員が多数見られました。
これは、学校教育における「郷土に誇りと愛着をもった豊かな心を育むこと」や、「予測困難な社会を切り開いていく力を備えた未来の担い手を育てること」という考え方との共通点があると思います。そんな教員として最も大切な使命感・情熱を再確認できた大変実りのある研修会となりました。
九里様、本当にありがとうございました。
8月23日 授業力アップ研修会 「仲間に学ぶ」



 8月23日(木)に、あさひ野小学校で授業力アップ研修会を行いました。この研修会の講師は、あさひ野小学校の水島真寿美先生でした。水島先生は、昨年度、「朝日町教育委員会派遣内地留学」で上越教育大学の阿部隆幸准教授の研究室に研修に行かれ、「ファシリテーションスキル」「アクティブラーニング」「学び合いの仕組み」について深く研鑽を積んでこられました。まさに、新学習指導要領にある授業改革の方法を、ご教示いただく貴重な研修会でした。
8月23日(木)に、あさひ野小学校で授業力アップ研修会を行いました。この研修会の講師は、あさひ野小学校の水島真寿美先生でした。水島先生は、昨年度、「朝日町教育委員会派遣内地留学」で上越教育大学の阿部隆幸准教授の研究室に研修に行かれ、「ファシリテーションスキル」「アクティブラーニング」「学び合いの仕組み」について深く研鑽を積んでこられました。まさに、新学習指導要領にある授業改革の方法を、ご教示いただく貴重な研修会でした。
講演では、ファシリテーションスキルの理念や効果、学び合いを生み出す授業プログラムのコツについて、理論と実践例を結びつけて、丁寧に教えていただきました。また、グループワークでは、「ホワイトボードを使ったペアトーク」「カードを使ったお話づくりゲーム」「グループで協力し合うクイズゲーム」等の活動を通して、協同で活動する楽しさや真剣に聞いてもらうことから生じる満足感や有用感を、身をもって実感しました。このように、すぐに実践できる手法を例示していただいたおかげで、2学期からの学級づくり・授業づくりに生かしていこうという意欲をもった参加者が多数見受けられました。
先生方。2学期は、この研修会で学んだ子供たちに「配慮して、遠慮しない」を胸に、積極的に新しい授業をデザインしていってください。そして、「失敗は成功のもと」「為せば為る」そんな前向きな意識をもち、教員も協同で指導のスキルを高めていきましょう。
8月9日 現地学習会 「郷土の地質・化石について学ぶ」





 8月9日(木)に朝日町現地学習会「郷土に学ぶ」を開講いたしました。この研修会は、町の郷土教育教材開発研究調査員会が中心となって、地域の歴史・文化への理解を深めるために、郷土の史跡や施設等の見学や体験活動を行うもので、毎年開催されている朝日町の特徴的な研修です。
8月9日(木)に朝日町現地学習会「郷土に学ぶ」を開講いたしました。この研修会は、町の郷土教育教材開発研究調査員会が中心となって、地域の歴史・文化への理解を深めるために、郷土の史跡や施設等の見学や体験活動を行うもので、毎年開催されている朝日町の特徴的な研修です。
今年度は、「郷土の地質・化石について学ぶ」というテーマの下、特別講師に朝日町教育委員会 学芸員 久保 貴志 氏をお招きして調査員とともにご教示いただきました。
研修では、笹川地区の岩石の変化や、鹿嶋神社の溶岩流からできた地層を観察しながら、東アジアでは珍しい地層の存在や日本列島の成り立ちについて学習しました。 また、大平地区・市振地区の地層の観察の仕方や境川河口での化石発掘の仕方等、実際に子供たちにどう学習させたらよいかという具体的な提案を調査員の方からいただきました。
参加者からは、「朝日町は、地層の宝庫であると聞いて、ここで働くことに誇りをもちました。」「地層観察も化石掘りも実際に見て、聞いて、体験できて本当によかったです。久保先生の熱弁もすごくて、興味がそそられ、私も調べてみたいと思いました。」「久保さんのメッセージ「理科を通して生命の尊さを教える。」ぜひ子供たちに伝えていきたいです。」といった感想がありました。
最後に長谷川委員長がこうおっしゃいました。
「今日の研修で学んだことを、ぜひ朝日町の子供たちに体験させてほしい。伝えてやってほしい。それが、朝日町を愛する心豊かな子どもの育成につながるはず。ぜひお願いします。」
子供たちが、郷土のよさを感じるためには、私たち教師がその良さを知ることが大切だと改めて感じる素晴らしい研修会でした。
8月7日 授業力アップ研修会 楽しい理科実験を体験!




 8月7日(火)に授業力アップ研修会(理科実験)がさみさと小学校理科室で行われました。この研修会は、理科の授業力の向上を目的に、町内の小・中学校の先生方が集まって体験型の研修を受講していただきました。講師には、富山県総合教育センター 科学情報部の主事をお招きして「電熱線」と「ゴム」の2つの研修を開講していただきました
8月7日(火)に授業力アップ研修会(理科実験)がさみさと小学校理科室で行われました。この研修会は、理科の授業力の向上を目的に、町内の小・中学校の先生方が集まって体験型の研修を受講していただきました。講師には、富山県総合教育センター 科学情報部の主事をお招きして「電熱線」と「ゴム」の2つの研修を開講していただきました
研修①では、「電熱線の発熱実験」を体験しました。小学校6年生の単元の中にある「発砲ポリスチレンの板を電熱線で切る実験」を行う際に、妥当な実験結果を得るためには、電池ではなく電源装置を利用し、切れるまでの所要時間を記録するとよいことを学びました。また、手回し発電機を活用して、抵抗と電流、電圧の関係を改めて学びました。
研修②の「ゴムで動かそう」では、小学生でも簡単に作ることができる「ゴムの伸縮・ねじれを利用したおもちゃ」をつくりました。1つは、「もどり車」、もうひとつは、走るカップ虫でした。受講した参加者は、子供になりきり、丁寧に実験・制作を行ったり、完成した作品を動かして喜びの声を上げたりして、理科の楽しさを堪能しておられました。
感想からは、「電圧の変化する電池ではなく、電源装置を使って、電圧を一定にして実験するとねらった結果が求められうことが良く分かりました。」「実験機器の使い方や、比較実験を行う際の準備物について実物を使って体験することでよく分かりました。」「身の回りにある材料を生かしたおもちゃ作りをすることで、学習内容の理解や思考が深まり、興味の広がりにつながると感じました。ぜひ子供たちとやってみたいです。」といった意見がありました。
今日は、先生方の笑顔が絶えない楽しい研修会でした。
理科の楽しさを子供たちに味わわせるためには、教師自らが理科を好きになることが前提にあるのではないでしょうか。「準備が大変。実験が難しい。安全面に不安・・・。」というマイナスイメージばかりをもつのではなく、こういった研修で方法を学んだり、総教セ等のHPや書籍でちょっと調べることで、「より簡単に、安全で分かりやすい実験や工作」を子供たちに提供することができるのです。難しく考えないで、まず先生が笑顔で理科を実践してみてください。きっと「理科好きの子」が増えると思いますよ。
8月6日 学力向上プログラム研修会「深く考え、議論し、心が動く道徳の創造」を学ぶ
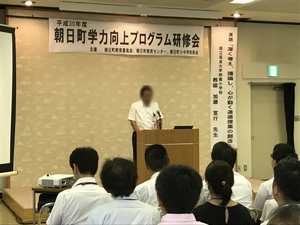


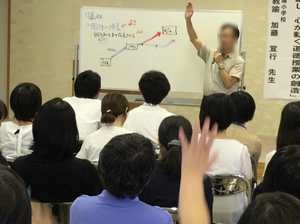
 8月6日(月)には、「朝日町学力向上プログラム研修会」が開かれました。
8月6日(月)には、「朝日町学力向上プログラム研修会」が開かれました。
今年は、今年度小学校で教科化された「特別の教科 道徳」に着目し、指導力の向上を図ろうと考え、企画いたしました。 講師には、光文の教科書編集に携わっておられる筑波大学附属小学校の加藤 宣行先生をお招きして「深く考え、議論し、心が動く道徳の創造」という演題の下、模擬授業形式でご講演いただきました。
加藤先生から教えていただいた中で、特に印象に残っていることは以下の内容でした。
①教科化の真の目的は、『積極的な道徳→生活・学びにやる気が出る→心が豊かになる・生きる力が育つ(生活習慣が整う・教科の学力が伸びる等)こと』であること
②従来の読み物道徳から脱却するためには、C型(テーマ発問型)もしくはKTO型を意識して取り組むことが大事であること。そのために一番大切なことは、『内容項目・教材・真の問い』の研究が必要不可欠であること。
③板書の工夫は、子供の思考をサポートするツールとして重要であること
④道徳ノートの活用によって、自己評価・自己指導が生まれること
⑤道徳の評価をする際に、目的(意味づけ・賞賛・承認)、方法(形成的評価・見取り)、観点(態度評価)を明確にもつことが重要であること
加藤先生は、「道徳という教科は、日本特有のもの。常識や価値観についてとことん考え、話し合う機会はめったにない。それができるのが道徳である。道徳は、子供の重しになるのではなく、よりよく生きる道を開放させるための道しるべになる。」とおっしゃっておられます。
私たち教師も、道徳を重しに考えるのではなく、よりよく生きる道を開放させるための教科として臨んでいくことが大切であると考えます。道徳の授業に求める子供たちの姿と同様に、教師も失敗を恐れず、積極的にチャレンジしていきましょう。
8月3日 情報教育研修会「プログラミング教育の理念と指導法を学ぶ」

 8月3日(金)に朝日町情報教育研修会が開かれました。
8月3日(金)に朝日町情報教育研修会が開かれました。
この研修会は、朝日町情報教育研究調査員が講師となり、より効果的なICTを活用した指導方法を町内の先生方に提供するために毎年開かれております。
今回の研修では、新学習指導要領の目玉の一つである「プログラミング教育」をテーマにおいて研修会を行いました。
まず、オリエンテーションでは、内山委員長に「プログラミング的思考力の概念と必要性」について先生方に分かりやすくプレゼンをしていただきました。
次に、研修1では、アンプラグドによる掃除手順表の制作実践、研修2ではビジュアルプログラミングの実践として「プログラミン」の活用、研修3では、フィジカルプログラミングの実践として「SPARK+」の活用について、調査員が中心となって説明し、受講者に子供たちの立場になって実践していただきました。
感想からは、「プログラミングと聞くとデジタルをイメージしてしまうが、アンプラグドによるアナログ的な活動を通して思考力を育てることが参考になりました。ぜひ2学期に実践したいです。」「「プログラミング的思考力を意識した授業づくりに取り組むと、教員自身の思考力・伝達力の向上にも通ずるということがとても納得がいきました。子供たちにいかに簡潔に分かりやすく伝えるかを今一度見直したいです。」といった意見が多く聞かれました。
 「プログラミング教育」は、今もう始まっています。「プログラミング的思考力・論理的思考力」を育成するために、まず簡単なアンプラグドによる実践に挑戦してみることが大切です。新学期、ぜひ挑戦してください。
「プログラミング教育」は、今もう始まっています。「プログラミング的思考力・論理的思考力」を育成するために、まず簡単なアンプラグドによる実践に挑戦してみることが大切です。新学期、ぜひ挑戦してください。 
8月1日 外国語活動に関する講演会 「教科化に向けての新しい英語指導法を学ぶ」



 8月1日(水)には、魚津地区教育センター協業講演会が開かれました。今回は、東京学芸大学 教授粕谷恭子先生をお招きして、「外国語活動に関する講演会」が行われました。
8月1日(水)には、魚津地区教育センター協業講演会が開かれました。今回は、東京学芸大学 教授粕谷恭子先生をお招きして、「外国語活動に関する講演会」が行われました。
「新学習指導要領に応じたこれからの英語指導は、どうあるべきか。」
粕谷先生には、今、現場の先生方にとって一番の不安となっている点に焦点を当てて講演していただきました。
講演の中では、「聞きたい・読みたい・話したい・書きたい」といった子供たちの心と思いを中心とした授業づくりに心がけること」「子供に力を付けるための技能指導の順序」「英語教育の基盤となる音声経験の重要性」「意味と音を結びつけやすい話題・題材・場面状況づくり」「従来のゲームから意味のある活動への転換」「担任は、授業・子供を守る人」等といった内容を、実践を交えて的確に示唆いただきました。
受講者からの感想には、「音声言語がどれだけ重要かが分かりました。音をシャワーのように聴かせることで、発話につながって行くのだと痛感しました。」「言葉に命を吹き込むことの大切さを教えていただきました。本来の生きている文脈の中で、子供が英語を遣う活動がとても重要だと感じました。」といった新しい見方考え方に気付かされたという意見が多く聞かれました。
道徳科、外国語科、プログラミング教育等、戦後最大の教育改革がもう始まっています。
新しい時代に対応した教育が求められる中、私たち教員もこういった生きた研修を行い、それをヒントに新しい資質・能力を育てる指導法を共同研究と協働実践で切り開いていきましょう。
7月27日 さみさと小学校校内研修会 「協同的な学び合い」



 7月27日(金)には、朝日町立さみさと小学校の校内研修会に参加いたしました。
7月27日(金)には、朝日町立さみさと小学校の校内研修会に参加いたしました。
今年度も、上越教育大学教職大学院 准教授 阿部孝之先生をお招きして、「協同的な学び合い」についてご教示いただきました。
講演会の中では、「主体的な授業をつくるための条件は、子供に裁量権があること」「学び合いの主体は子供であるから、目標-学習-評価の一体化を図るべきであること」「ゲーミフィケーションを授業にうまく取り入れることが重要であること」「教師がファシリテーターとなって、子供たち主体の活動中心の授業を作り出すこと」等、具体的な授業事例を基に教えていただきました。
8月23日には、朝教セ主催の授業力アップ研修会「仲間に学ぶ」が開かれます。この研修会の講師あさひ野小学校の水島先生は、内地留学で阿部先生の元で学んでこられた内容を伝達してくださります。今日の研修会と同様、内容の濃い実践的な研修になると思います。ぜひ、ふるってご参加ください。
