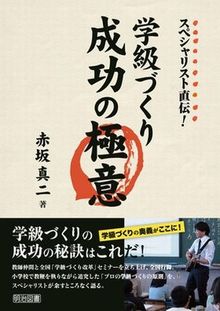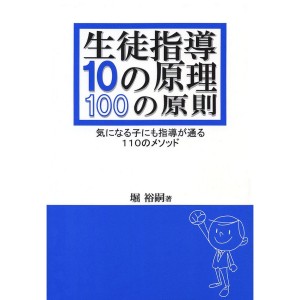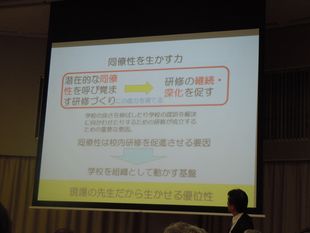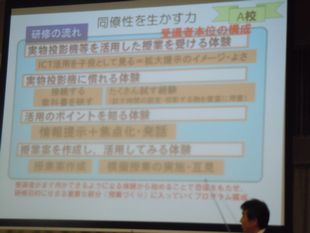今年度から新たに始まった「会」です。学校の研究・研修と柱である研究主任の先生は、意外に集う機会がありません。校長会、教頭会や教務主任会との話題の共有、町としての取組情報を知る機会となっています。今年度に関しては、「授業リフレクション」の手法を取り入れた事後研修の方法を3校同時に実施し、アドバイスし合って進めることができました。次年度に取り組んでみたいこととして、
○教具(ホワイトボード等)の効果的な使い方
○授業終末の充実
○テンポのよい学習規律のスタイル確認 などが上がっています。
投稿者「朝日町教育センター」のアーカイブ
研究主任会
合同調査員会
1年間ご活動いただいた「情報」「郷土」の両調査員の先生方が一同に介しての、最後の調査員会でした。「情報」では、とくに子どもたちを取り巻くネットワーク環境の進化に対しての継続調査の必要性が、「郷土」では、朝日町にある素晴らしい郷土教育教材をいかに広め、残していくかという課題について活発な議論がなされました。両委員会とも調査してこられたことを、次年度は授業という形で検証していくという共通の方向性が見えました。調査員の先生方、1年間ありがとうごうざいました。
外国語活動推進委員会
「外国語活動推進委員会」の最終会合がありました。
ALT、外国語活動指導員を交えて、今年度の小学校の「外国語活動」について意見交換をしました。朝日町の小学校高学年の授業を見ていますと、よく身につけていると感心するのですが、指導者からは音声言語が中心であるため、子どもたちは理解しにくいだろうという問題意識が高く、中学「英語科」との違いとつながりについて、活発な意見を交わされました。
委員のみなさん、1年間ありがとうございました。
まとめの時期
先週は、情報、郷土の2つの調査員会の最後の会合があり、1年間の報告をする「合同調査員会」に向けての1年間のふりかえりと次年度の方向性について話し合っていただきました。
朝日町独特の小中高生徒指導連絡協議会 も最後の会合を行い、各校生徒指導主事の先生からの「1年間の取組」を報告いただき、検討と情報の共有を行いました。
来週は、教務主任会、研究主任会、外国語活動推進委員会のまとめが行われます。
もう、そんな時期なんですね。
明けましておめでとうございます
2013年。平成25年になりました。
明日は、いよいよ始業式です。長かった冬休みも終わりました。
教育センターの窓からは、雪と空のコラボレーションが、その日によって違い、なかなか素敵です。
本年もどうぞよろしくお願いします。

学級づくり成功の極意
冬休みに入っても出勤しておられる先生方も多いですね。でも、この冬季休業中の間に、研究紀要の執筆とともに、3学期の「戦略的構想」を練られることでしょう。センターは、最近の教育書の執筆者が若返っています。しかし、授業づくりネットワーク世代と教師塾世代に、TOSS世代も健在の、3世代が混在するのは、やはり急激な大量退職、大量採用時代への要求がそこにあるように思えます。
さて、当センターの課題ですが、そんな現在売れている教育書の執筆者が、大事にしておられること、具体的な主張は何なのかを見て、共通性を見ています。そのことで、現在の学級づくり、学年づくり、授業づくりへの有効な思想、哲学、方法が見えてくるのではと思っています。
赤坂真二先生の本が、教育センターに3冊あります。「学級づくり成功の極意」を読み直してみました。アドラー心理学を基盤にもっておられるので、個や集団への配慮が抜群です。この点だけでも、見習える内容が豊富です。第2に、希に見る、抜群の小学校教師でした(今は、准教授なので)。学級づくりの実践と考え方を見れば、圧巻の教師の姿があります。集団をつながりをつける手法は、書籍や講座でもいろいろありますが、なかなかいいものばかりではありません。本書には、良質のグループ体験のアクティビティが、すぐ使えるようになっています。私が一番気に入ったのは、「機嫌のいい教師」と「叱ること」についてでした。読んで納得はするが、明日の学級には変化が起こらない本もありますが、明日が変わる1冊です。冬休みに、ぜひどうぞ!
学校は冬休み中です
小中学校が冬季休業に入りました。
教育センターも、より静かになりました。
昨日、授業DVDや教育書を借りに来られた先生もおられました。
「なかなか観られなかったので、冬休みに観ようと」という先生もおられることでしょう。
町教育センターは、平成24年は、12月28日(金)まで。新年は、1月4日(金)から開いています。
それでは、皆さん(誰?)、よいお年を。

気になる教育書
センターでの図書購入は本年度分は終了しております。今年度は、けっこう新刊を購入しました。一度、ご覧いただければと思います。大量退職、大量採用の時代が到来したからでしょうか、教育書が売れているようです。新しい著者も多く登場しています。
センター所員は、個人的に買って読んでいる本を少しずつ紹介いたします。お忙しい先生方は参考にしていただければと思います。
「堀 裕嗣」先生はご存じでしょうか。最近、すごいペースで本を出しておられます。「10の原則 100の原理」シリーズが人気ですね。月刊「生徒指導」でも執筆しておられますし、今頃は毎週、講座や講演で飛び回っておられるうようです。「生徒指導10の原理・100の原則」は、中学校向けの生徒指導の本ですが、小学校高学年からの「かわいらしさから変容しつつある」頃の子ども集団の見方には参考になると思います。風貌も体格もいい堀先生の生徒指導は、「毅然とした指導」一辺倒ではありません。だから、小学校の先生にもいいのです。
「もし、私たちが教える方法で子どもたちが学ぶことができないなら、私たちは、彼らが学ぶことのできる教え方を学ばねばならない」という文を引用されるぐらいで、けっこう理論的な生徒指導ですが、読みやすい一冊です。