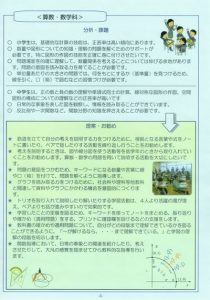情報教育研修会を行いました。今回は、児童生徒の学習に生かす効果的なタブレット活用~「小学校低学年でも30分でできるプレゼン」(ロイロノートの活用)、「AirDrop を使おう」、「その場で作れるKeynote」~ この3点について研修しました。

情報教育研修会
ロイロノートを活用することで、撮る、調べる、書くなどの活動が容易にできます。そうやって取り組んだ自分の学習を一つのノートにまとめることができます。さらに、一人一人の考えを即時にクラスで共有し、話合いにつなぐことができます。
AirDropの機能を使うことで、子供同士、子供と先生の間で画像を転送することができます。生活科や理科、社会科等の見学や観察学習で見つけたことや分かったことを即時に共有し、比較することができます。
Keynoteは、PCが無くてもタブレットでプレゼンテーションが作成できます。また、撮影した画像をプレゼンに組み入れることができます。AirDropの機能を使えば、プレゼンを共有することもできます。
このようにタブレットは、児童生徒が自分の考えをまとめることや互いの考えを視覚的に共有することなどに効果的に活用できます。児童生徒が学習をアクティブに進めるための支援の一つとして、タブレット活用の推進を考えていきたいと思います。