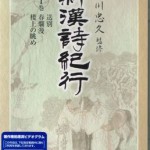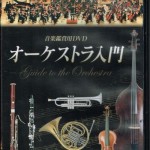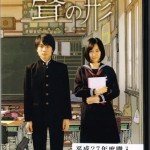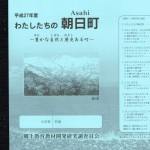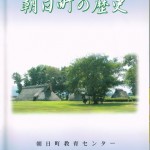第3回研究主任会を行いました。今年度、最後になります。
各校では、校内研修を通じて、授業力向上や健康づくり等の研究に取組んでおられます。
小学校では、学び合う学習を仕組むために、ペアやトリオ、グループによる活動を位置付けています。そうすることで、分からないところを気軽に聞き合ったり、自分の考えを説明したり教えたりすることが身に付いてきました。また、授業の基礎となる学習規律の確立も図られています。学習の準備を整えて授業に臨む、友達の話に耳を傾けて聴くことなどを身に付け、集中して学習に取組んでいるとのことでした。
心と体の健康づくりに取り組んでいる小学校では、健康づくりのキャッチフレーズ「みんなでまめなけ あさひ野っ子」が全校に浸透したことで、よい姿勢やけがの防止など、健康づくりの活動に自分事と考えて取組む姿勢が見られるとのことでした。
中学校では、互見授業が実践されました。授業の前に、互見授業の視点を全体に周知することで、教科をこえて参観することができた、また、参観カードを活用することで、授業者は授業改善につなげることができたとのことでした。
各校の研究は、どれも学力の向上、児童生徒の育成につながる効果的な実践です。この会で情報交換したことを各校及び町教育センター等の研修で広めていきたいと思います。