来る6月22日(金)にH30年度朝日町小中教育講演会が開催されます。
今年度は、埼玉大学教育学部教育学講座 准教授 北田佳子先生をお招きし、「これからの学校を担う教師像」という演題の下、教師の資質向上・意識改革を目的とした講演会が開かれます。講演会の中には、グループワーク等の実践的な研修も取り入れ、子供たちに即還元できる講演内容となっております。他市町村からもぜひ、ご参加ください。お問い合わせは、朝日町教育センターまで。
来る6月22日(金)にH30年度朝日町小中教育講演会が開催されます。
今年度は、埼玉大学教育学部教育学講座 准教授 北田佳子先生をお招きし、「これからの学校を担う教師像」という演題の下、教師の資質向上・意識改革を目的とした講演会が開かれます。講演会の中には、グループワーク等の実践的な研修も取り入れ、子供たちに即還元できる講演内容となっております。他市町村からもぜひ、ご参加ください。お問い合わせは、朝日町教育センターまで。
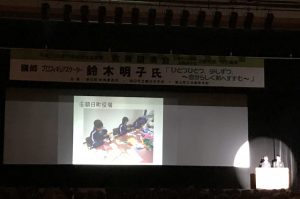

 11月15日(水)に朝日町中高教育講演会が開かれました。朝日町は、小学校2校、中学校1校、高等学校1校と少数である特徴を生かし、毎年様々な連携事業を行っています。この「中高連携事業」も毎年工夫されており、学習活動・部活動・進路探訪等、朝日町ならではの交流事業が行われています。
11月15日(水)に朝日町中高教育講演会が開かれました。朝日町は、小学校2校、中学校1校、高等学校1校と少数である特徴を生かし、毎年様々な連携事業を行っています。この「中高連携事業」も毎年工夫されており、学習活動・部活動・進路探訪等、朝日町ならではの交流事業が行われています。
今年の「中高教育講演会」では、朝日中学校の・泊高等学校の特徴的な学習活動をプレゼンにまとめて発表し、お互いのよさを交流しました。
朝日中学校は、「14歳の挑戦」の取組を2年生の代表が堂々と発表しました。泊高等学校は、特色ある学科である観光ビジネスコースの生徒が、「観光故郷の道と暮らしの移り変わり」について詳しく発表しました。どちらの発表も未来を担う若者と地域社会との連携を密にした取組で、朝日町のつながりを感じる素晴らしいものでした。
後半は、特別教育講演会が開かれました。今年の講師は、プロスケーターの鈴木明子さんでした。鈴木氏は、「ひとつひとつ。少しずつ。~自分らしく前へ進む~」の演題の下、オリンピックへの厳しい道のり、拒食症という難病との闘う苦悩、失敗を恐れず常に理想を目指す意識への転換、支えてくれた多くの人々・家族・仲間への感謝、これから未来への希望等、自身の味わってきた体験談を赤裸々に語ってくださいました。鈴木氏の感情のこもった講演に、会場の観衆もあたかもそのスケートの世界を経験しているかのように、心の奥まで響いてくる講演会でした。
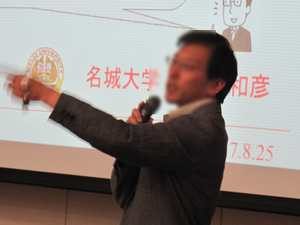 8月25日、魚津地区教育センター協業事業 である「生徒指導に関する講演会」が開かれました。今年度は、講師に名城大学 教授 教職センター長であられる曽山 和彦先生をお招きして開演されました。
8月25日、魚津地区教育センター協業事業 である「生徒指導に関する講演会」が開かれました。今年度は、講師に名城大学 教授 教職センター長であられる曽山 和彦先生をお招きして開演されました。
曽山先生は、特別支援教育の方向から、どの子供にもできる指導法を伝授してくださいました。特に印象的だったのは、ルール作りやふれあいづくりの際に、否定する場合も肯定する場合も、「あなたは、・・・ (YOU)」で伝えるのではなく、「私
(YOU)」で伝えるのではなく、「私 は、・・・(I メッセージ)」という立場で伝えると効果的であることを教えていただいたことでした。「先生に共感してもらえている。」「期待してもらえている。」と感じることで、先生との関係(縦糸)を結びたいと歩み寄ってくることが分かりました。これは、どの教師も即実践できるスキルであると同時に、「根本は、児童生徒理解・子供との関係づくり」という最も大切なことを再確認できた研修であったと思います。
は、・・・(I メッセージ)」という立場で伝えると効果的であることを教えていただいたことでした。「先生に共感してもらえている。」「期待してもらえている。」と感じることで、先生との関係(縦糸)を結びたいと歩み寄ってくることが分かりました。これは、どの教師も即実践できるスキルであると同時に、「根本は、児童生徒理解・子供との関係づくり」という最も大切なことを再確認できた研修であったと思います。
誰もが安心して学べる空間づくり」これこそが、子供の求めている教育であり、学力・体力・社会性を身に付ける上で、最も大切な生徒指導であると教えていただきました。
多数の方にご参加いただき、まことにありがとうございました。
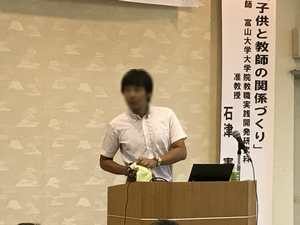


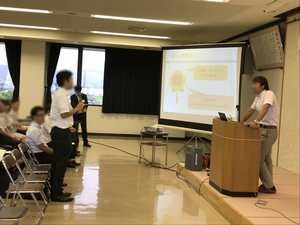 8月18日(金)に朝日町小中高教育講演会が開催されました。今年度は、富山大学大学院教職実践開発研究科 准教授 石津 憲一郎先生をお招きし、「子供と教師の関係づくり」という演題でご講演をしていただきました。
8月18日(金)に朝日町小中高教育講演会が開催されました。今年度は、富山大学大学院教職実践開発研究科 准教授 石津 憲一郎先生をお招きし、「子供と教師の関係づくり」という演題でご講演をしていただきました。
石津先生は、『子供の心を開くためには、「自立とエネルギー」「安心と安全」が必要である。子供自身のエネルギーは、関係性・有能性・自律性の3つの歯車がかみ合い、動きださなければ生まれてこない。そのために、教師が「対話・心情・関心・共有」によって安心・安全な関係をつくることが大切である。体験活動は、その関係性を作るきっかけをつかむのに適しているので、積極的に取り入れるとよい。』と、教えてくださいました。
後10日間で、「学校行事等の多い2学期」が始まります。この石津先生に学んだことを各校で実践し、子供との関係づくりを積極的に進めることで、たくさんの子供の心の歯車が回り、のびのびと活躍してくれること期待しています。



 夏休みに入ってはや1週間が経ちました。8月の研修のトップバッターとして「朝日町学力向上プログラム研修会」が開催されました。今年度は、筑波大学附属中学校 教諭 岡田 幸一先生をお招きして行いました。
夏休みに入ってはや1週間が経ちました。8月の研修のトップバッターとして「朝日町学力向上プログラム研修会」が開催されました。今年度は、筑波大学附属中学校 教諭 岡田 幸一先生をお招きして行いました。
岡田先生は、「生徒が読みもの(小説等)を好きになる学習を作り出すためには?」「子供たちが主体的に読み深めていくアクティブラーニングとは?」ということを中心に、自らの中学校での実践からつくられた多数の資料を基に、具体的な手立てと方法を示してくださいました。また、後半には、模擬授業形式で短編小説の中から「問い・キーワード」を見付ける活動を先生方に生徒役として参加していただき挑戦していただきました。思った以上に一人一人の問いが多様性に富んでいることが実感させられました。
先生方の感想からは、「問いを大切にして子供たちに任せてみることを挑戦してみたい。」「主体的な学習を生み出すためには、授業者の十分な構えが必要である。その裏側の努力とよさを感じさせていただいた研修会だった。」など、岡田先生の読み深める活動に刺激を受けた参加者が多く見られました。
「主体的・対話的で深い学びとは何か?」
一人一人の先生方が、各専門教科において教科研究を重ね、授業改善を図っていく必要性を感じた研修会でした。



 7月31日(月)に外国語活動研修会が開かれました。講師に、文教大学教育学部 教授 金森 強先生をお招きして「新学習指導要領に応じた英語指導の在り方」について学びました。
7月31日(月)に外国語活動研修会が開かれました。講師に、文教大学教育学部 教授 金森 強先生をお招きして「新学習指導要領に応じた英語指導の在り方」について学びました。
金森先生は、「これからの教育に求められることは、新しい知識を知ることよりも、活用する方法を知ることや、目的・場面・相手・状況等に応じて考えて行動する力をもつことである。よって、従来の英語教育の発想を大きく変えなければならない。そのためには、小学校の楽しむ・親しむ外国語活動の考え方を大切に英語好きの子供たちを育てていってほしい。」と、強く望まれていた。
「外国語の意味が知りたい。外国人と話したい。文字を書いて伝えたい。」そんな願い・目的意識をどうやってもたせるのか。これが、これから求められる新学習指導要領における「教師の指導力」なのだということが明確となった研修会でした。



 6月22日に朝日町小中講演会が開催されました。本年度の講師は、東北福祉大学教授 上條晴夫先生をお招きし、「理想の授業づくりに必要なこと」という演題でご講話をいただきました。
6月22日に朝日町小中講演会が開催されました。本年度の講師は、東北福祉大学教授 上條晴夫先生をお招きし、「理想の授業づくりに必要なこと」という演題でご講話をいただきました。
上條先生は、教師教育に視点をおかれ研究されており、「理想の授業づくりに大切なこと」は、自分の強み・好きなこと・価値観を見つめ、それを軸としてアクションとリフレクションを繰り返していくことが大切であること。若手とベテランが融合するためには、それぞれのコア・クオリティー(本質~強み・好み・価値観など)を理解し合うこと等を教えていただきました。
その後のワークショップでは、まずペアとなり、「過去に体験した理想の実践」を語り合い、その相手の方の強みを見付けて伝える活動をしました。次に、4人組となり、話を聞いた相手がそのペアの実践と強みを紹介する活動をし、グループで4つの理想の実践と4人の強みを共有しました。この演習を通して、先生方の表情が、何かすっきりとし、自信に満ちた様子がうかがえました。まさに、上條先生が冒頭におっしゃった「まず先生が笑顔で元気に」という形で講演会を終えることができました。
講演会後のアンケートでは、「自分の強みを知り、それを授業に生かす。そうすると、自分も子供も楽しく学ぶことができるということを改めて感じ、ちょっと元気になりました。また、若手とベテランの意識の違い・溝のようなものに悩んでいましたが、それがなぜなのか少し分かったように思います。」といった今後の授業づくり・教師同士の人間関係づくりの向上につながる意見が多くありました。
清々しい空の下、素晴らしい講演会となりました。ご協力ありがとうございました。
魚津地区教育センター協議会による今年度3つ目の講演会、「道徳に関する講演会」を行いました。
講師には、東京学芸大学教職大学院 教授 永田繁雄先生をお招きしました。演題は「心を育てる学校教育」、サブタイトルは「道徳の『特別の教科』化時代に私たちが取り組みたいこと」これは、今まさしく、どの先生方も学びたいと思っておられる事柄であり、タイムリーなタイトルだと思います。

道徳に関する講演会
先生からは、道徳の教科化が求められる背景や、「特別の教科 道徳」の目標及び内容と評価の在り方、さらには、「考え、議論する」道徳の授業を実践する際の考え方及び留意点等について、具体的な事例を通してご教授いただきました。
指導いただいた内容のひとつに、子供たちの「多面的・多角的思考」を育てるために、認め合い、磨き合う授業を推進することを示していただきました。そのためには、仮説を立てる、関連づける、論じる、説明する、身近な問題に適応する、振り返るなどの学習活動が重要になります。このことが確実に行われている授業が、私たちに求められるのだと思います。
「特別の教科 道徳」についての考え方と取り組みたい授業の形とをリンクさせながら指導していただいたので、とても分かり易い講演でした。講師の先生には感謝申し上げます。
朝日町小中学校教育講演会を行いました。講師には、東京学芸大学教職大学院 准教授 岩瀬直樹先生をお招きしました。
まず、信頼をベースとした学級経営の考え方を示していただきました。心の体力が温まるエンパワメントな人間関係をつくること,子供たち一人一人のコミュニケーション能力を育むことが重要であることを示唆いただきました。

小中学校教育講演会
次に、演習を通じてオープン・クエスチョンやホワイトボード・ミーティングを活用した指導法を体験しました。これらを用いて聴くことで、客観的に相手の状況や気持ちがイメージでき、共感することができました。そうしたことで相手と一緒に考え合おうとする関係ができました。
共に考え合い、解決策を探る。そうやって見つけたことを友達と一緒に実践するので、子供は自分事として取組み、仲間意識を大切にしていくのだと思いました。
また、「オープン・クエスチョンは、クラスで○○回位練習しました。」という言葉をお聞きし、子供たちを支援するために教師としての信念を持つこと、相手を信頼することの大切さを重ねて教えていただきました。
講師の先生には感謝申し上げます。
今年度の朝日町小中学校教育講演会を6月17日(金)14時40分より、朝日町役場4階大ホールにて行います。講師は東京学芸大学 准教授 岩瀬 直樹 先生です。演題は、「信頼関係をベースとした学級経営と教師の役割」です。
岩瀬先生は、全国の学校を参観する中で、組織論、クラスづくり、授業の改革の必要性を感じ、実践研究を始められました。授業や日々の生活場面で子どもたちが笑いあい、助け合い、学び合い、高め合うことができる「信頼ベース」のクラスづくりを提唱されております。
教育講演会を通じて、学級経営についての考え方、子どもが主体的に学ぶ授業、日々の学校生活をつくる支援等について、学びたいと思います。
講演会については、チラシをご覧ください。