第2回学力向上推進委員会を行いました。当委員会は、当町の児童生徒の全国学テの結果から学習指導の参考となるポイントや学習規律の確立に向けての取組等を示しています。今年度は、全国学テの結果分析を参考に、授業改善及び人間関係・学級づくりにつながる学力向上策を示すこととしました。

学力向上推進委員会
一つは、「ホワイトボードの効果的な活用」です。ペアやトリオ、グループでの話合いなどに活用することで思考を可視化でき、他者との交流・協働につながると思います。また今年度の研修で、東京学芸大学 准教授 岩瀬直樹先生から指導いただいた、オープンクエスチョンとホワイトボード・ミーティングを活用した指導の在り方についても、併せて示したいと思います。
もう一つは、「人間関係・学級づくり」のための手立てです。スキル・トレーニングの考え方や方法等を示し、学び合う学級づくりを支援したいと考えています。併せて、今年度の研修で指導していただいた、クラス会議についても示したいと思います。
県の学力向上推進チームから、9月に学力向上に係るリーフレットが発行されております。その中に、「何を覚えたかではなく、どんなことができるようになったかへシフトチェンジ」というキーワードがありました。
このことから、学力向上推進委員会でも、他者との交流・協働につながる指導のポイントを示し、児童生徒がアクティブに学ぶための授業改善の一助としたいと思います。



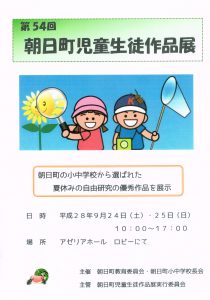 9月24日(土)、25日(日)、朝日コミュニティーセンター「アゼリア」で、児童生徒作品展を行います。ここには、朝日町の小中学校から選ばれた夏休みの自由研究の優秀作品が展示されます。
9月24日(土)、25日(日)、朝日コミュニティーセンター「アゼリア」で、児童生徒作品展を行います。ここには、朝日町の小中学校から選ばれた夏休みの自由研究の優秀作品が展示されます。





