3月16日には、朝日町内の2小学校で卒業証書授与式が挙行されました。私は、その内の一校、さみさと小学校の式に参加させていただきました。
 卒業生入場。温かい拍手の中、60名の卒業生が胸を張って入ってきました。その姿は、とても頼もしく、落ちついていました。式中も、素晴らしい返事、素晴らしい態度、素晴らしい眼差し・・・。卒業生も、在校生もこの1年でさらに成長したことを証明しているかのようなとても立派な姿でした。
卒業生入場。温かい拍手の中、60名の卒業生が胸を張って入ってきました。その姿は、とても頼もしく、落ちついていました。式中も、素晴らしい返事、素晴らしい態度、素晴らしい眼差し・・・。卒業生も、在校生もこの1年でさらに成長したことを証明しているかのようなとても立派な姿でした。
お別れの言葉。「ビリーブ」「また会う日まで」「巣立ちの歌」に感動しました。素敵な歌詞を噛みしめるように丁寧に歌う姿から、12年間の成長の軌跡が思い出され、喜びと悲しみが込み上げてきた方も多かったのではないでしょうか。
ご卒業おめでとうございます。本当に立派な卒業式でした。君たちの成長を側で喜んでくださった方こそ、君たちを支えてきて くださった方です。そんな方々への感謝の心をこれからも忘れず、夢と希望をもって大きく羽ばたいていってください。

 朝日町立朝日中学校では、3月14日(水)卒業証書授与式が挙行されました。
朝日町立朝日中学校では、3月14日(水)卒業証書授与式が挙行されました。 の外国語活動を引っ張ってくれることでしょう。
の外国語活動を引っ張ってくれることでしょう。 郷土教育教材開発研究調査員会では、本年度の活動のまとめと、次年度への方針について具体的な話合いを行いました。
郷土教育教材開発研究調査員会では、本年度の活動のまとめと、次年度への方針について具体的な話合いを行いました。 1月19日に朝日町小中高生徒指導連絡協議会が開かれました。本会では、今年度の各校で取り組んできた生徒指導への取組を交流するとともに、町として取り組んでいる挨拶運動のこと、オンラインゲームやSNS等の利用による危険性・依存症のこと、万引きなどの犯罪から守る取組等、具体的な事例を基に、有効な指導方法について話し合いました。
1月19日に朝日町小中高生徒指導連絡協議会が開かれました。本会では、今年度の各校で取り組んできた生徒指導への取組を交流するとともに、町として取り組んでいる挨拶運動のこと、オンラインゲームやSNS等の利用による危険性・依存症のこと、万引きなどの犯罪から守る取組等、具体的な事例を基に、有効な指導方法について話し合いました。






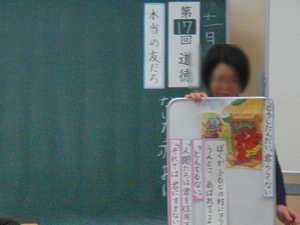
 11月29日(水)に、さみさと小学校に「授業の達人」事業で公開される授業を拝見しにお邪魔しました。その算数科の授業は、子供たちの関心・意欲が高まるストーリー式の問題提示、作業活動を取り入れた実感を伴う理解、グループ活動を取り入れた教え合いの活動、見に付けた力を実感する振り返りの工夫など大変よく練られており、指導の技(指導力)の高さを感じました。
11月29日(水)に、さみさと小学校に「授業の達人」事業で公開される授業を拝見しにお邪魔しました。その算数科の授業は、子供たちの関心・意欲が高まるストーリー式の問題提示、作業活動を取り入れた実感を伴う理解、グループ活動を取り入れた教え合いの活動、見に付けた力を実感する振り返りの工夫など大変よく練られており、指導の技(指導力)の高さを感じました。


 12月1日(金)に郷土教育研修会が、さみさと小学校で開催されました。今年は、初めて郷土教材を実際に取り入れた公開授業を調査員代表が行い、その提案授業を基に、郷土教材の活用法について考えていこうという試みをいたしました。
12月1日(金)に郷土教育研修会が、さみさと小学校で開催されました。今年は、初めて郷土教材を実際に取り入れた公開授業を調査員代表が行い、その提案授業を基に、郷土教材の活用法について考えていこうという試みをいたしました。