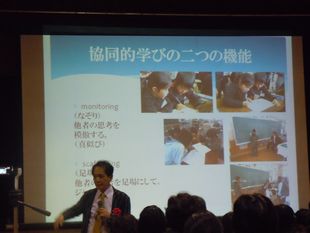「学び合い」を実践する学校の特徴がありました。
お気づきでしょうか。先生が前で座って授業をしています。背もたれのない椅子も校内で共通なんですね。とにかく先生の声が大きくならないように気をつけられているようです。子どもたちも座ったまま発言をしています。力まないようにでしょう。
どの教室にもロールスクリーン、プロジェクター、書画カメラはあります。電子黒板は、サイズ的に少し小さいでしょうか。
授業後の検討会です。校内の先生方だけで事後の検討会をしています。それを参観者が見守るというスタイルです。子どもたちの学びの検討というよりは、従来の事後研に近いものです。ただ、若い先生も含めて、全員が意見を述べられました。フリーカードよりも、厳しい指摘がなされていました。北田佳子先生の解説で、何を観ておられるのかが、とても参考になりました。この見方が変わらないと、授業は変わらないのでしょう。この実際に起きている学びの理解が難しいです。
佐藤 学 先生の講演。10年以上前に、佐藤先生の本にはまっていました。「僕は、大きな間違いをしていた」等。研究の中で、自分の見方がどんどん変わっていったことなど、いつも正直な方です。内容は、やっぱり刺激的です。おかげで、また佐藤先生の本を読み直しています。
県外の参加者も多く、富山市周辺の若い先生が熱心に参加しておられました。来年も奥田に行ってみようと思いました。朝日の先生方もいかがですか。