第52回 朝日町児童生徒作品展
日 時 9月27日(土)・28日(日) 午前10時から午後5時まで
場 所 アゼリアホール
▽作品展のポスターをご覧ください。 児童生徒作品展ポスター
爽やかな秋空の下、朝日中学校の体育大会が行われました。日頃の学校生活でも元気な挨拶が響き渡る朝日中学校ですが、この日も溌剌とした気持ちのよい姿が見られました。
まっすぐに伸ばした腕を力強く振っての入場行進、声をひとつに合わせ互いの健闘を誓い合うエールの交換、日頃から部活動等で鍛えてきた体を生かして走る200m走など、生徒の皆さんの体育大会に対しての熱意が各演技から感じられました。
競技への全力投球や一致団結した応援など、朝日中学校の伝統が、ずっと伝えられてきているのだと思います。
日 時 8月29日(金)
講 師 富山大学 教授 山西 潤一 先生
演 題 「学校の情報化に対応したICT教育の実践と評価」

講師 山西潤一 先生
朝日町小中高校教育研究協議会が主催する教育講演会が行われました。講師には、富山大学教授 山西潤一先生をお招きしました。
講演では、ICT機器を活かした学習方法や情報活用実践力の育成、共同活動の推進などについて、実践事例を通じて具体的に教えていただきました。また、情報教育のカリキュラムの立て方、評価基準の設定についても示していただきました。
さらに、授業でのデジタル教科書、タブレットの学習効果や無線LAN環境の整備、不正アクセス防止のための認証サーバーの必要性など、私たちが情報教育を推進していく中で取り組むべき課題を示唆いただきました。
山西先生、ご指導をいただき、本当にありがとうございました。
日 時 8月20日(水)
講 師 郷土教育教材開発研究調査員、まいぶんKAN学芸員
内 容 史跡、施設見学 <洋服工場、バタバタ茶伝承館、浜山玉つくり遺跡、御亭、一里塚、関の館>
町の史跡、施設などの見学や体験を通して、地域の歴史・文化への理解を深めることをねらいとして、郷土を学ぶ研修会(朝日町現地学習会)を行いました。盛夏のもと、研修会には多数の小中学校教職員に参加いただきました。
この日は、洋服工場をスタートに、バタバタ茶 、古墳時代の勾玉、江戸時代の関所などを見学し、町の産業、歴史・文化についての理解を深めました。
受講した教職員からは、「普段はそばを通り過ぎているにもかかわらず、詳しく知らなかった会社や史跡について学ぶことができた。特に、浜山玉つくり遺跡には、初めて足を運ぶことができた。この辺りは古くから文化が栄えていたのだと知り、感動した。」という声をいただくことができました。町の文化・歴史への興味を深める研修となったようです。
ご指導をいただいた、郷土教育教材開発研究調査員やまいぶんKAN学芸員の先生方、ありがとうございました。
日 時 8月18日(月)
講 師 立山カルデラ砂防博物館 学芸課長 飯田 肇 先生
演 題 「立山の自然の魅力」 ―雪の壁から氷河まで―

第2回学校教育運営協議会

講師 飯田肇 先生
立山カルデラ砂防博物館 学芸課長 飯田肇先生を講師にお招きし、第2回学校教育運営研修会を開催しました。
飯田先生からは、上昇する山、氷の山、火の山、水の山という視点から立山の様々な自然の魅力について、上空からの写真や調査活動などの映像を交えてお話をしていただき、3000M級の山々が連なる立山連峰の美しさ、80万年前の世界一新しい花崗岩の発見、日本で唯一現存する氷河などを教えていただきました。
富山県の代名詞とも言える立山の雄大な山並み、自然の魅力を認識させられるとともに、立山カルデラ砂防博物館研究チームによる内蔵助、御前沢雪渓などにおいての日本初の氷河の確認という偉業に感銘を受けるなど、郷土の山、立山連峰を誇りに感じることができた研修会となりました。
飯田先生、ご講演をいただき、深く感謝申し上げます。
日 時 8月12日(火)
講 師 トリノオリンピック アルペン監督 山中 茂 先生
演 題 「スポーツ指導で得た経験」

第1回 学校運営研修会

講師 山中茂 先生
学校運営や学級運営、その他今日的な教育の諸問題、社会問題についての理解を深め、教職員の資質向上を図ることをねらいとして、学校教育運営研修会を開催しました。講師には、トリノオリンピックアルペン監督 山中茂先生をお招きしました。
山中先生からは、長年のスキーを通した指導者としての経験談をもとに、コーチ、保護者、地域の方などが共通した意識のもとに、選手の指導に当たることの重要さと指導者としての要点を的確に教えていただきました。
参加した教職員の受講後の感想には、「チームワークの大切さは、教育現場でとても大切だと思い、共感しました。」「世界的アスリートを育てておられる山中先生ですが、優しい雰囲気をとても感じました。指導者というのは、強さ、厳しさだけでなく、先生のような寛大さも大切なのだと思いました。」「とてもバイタリティあふれる山中先生にパワーを分けてもらいました。前向きに人生を楽しむ姿は、うらやましくもあり、見習いたいです。」などの内容のものが多くありました。
山中先生、貴重なご講演をいただき、ありがとうございました。
日 時 8月11日(月)
講 師 国立教育政策研究所 教育課程調査官 笠井 健一 先生
演 題 「授業のねらいを明確にし、子どもの実態に合わせた授業」―算数・数学科―

国立教育政策研究所 笠井健一 先生

シェアリング
魚津地区センター協議会が主催する学力向上に関する講演会を開催しました。講師には、国立教育政策研究所 教育課程調査官 笠井健一先生をお招きました。
今回の講演で、先生からは、算数・数学科における言語活動の考え方や取り入れ方、学習のねらいを明確にもち、子供たち一人一人の実態に応じた到達目標を立て、その子供に合った言語活動を指導することの大切さ、評価の生かし方などを実際の授業の場面を想定しながら教えていただきました。
参加した教員の受講後の感想には、「思考力、判断力、表現力が個々の意味のものではなく、関連しているものであるということが理解できました。」「子供が学びの主体者となる授業とはどういうものか、課題提示、発問の仕方、適用問題などを具体的に示していただいたので、とても分かりやすかったです。」という内容のものが多く、笠井先生の講演によって大いに触発されたようでした。
笠井先生、実践的なご指導をいただき、本当にありがとうございました。
日 時 8月5日(火)
講 師 朝日町情報教育研究調査員
内 容 電子黒板機能付きプロジェクターを利用した授業展開、iPadの効果的な活用
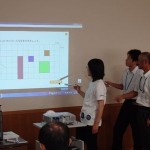
電子黒板機能付きプロジェクターの活用

iPadの活用
研修会では、情報教育研究調査員から、電子黒板機能付きプロジェクター、iPadの活用についての説明を行い、実技を通して指導に生かすスキルを体験していただきました。
参加した先生方からは、「電子黒板に触れることで、今後の授業で電子黒板を使ってみたいと思いました。また授業の幅が広がるように感じました。」「iPadで動画を再生するアプリは、体育のマットや跳び箱、なわとびなどで活用できると思います。」という声をいただきました。2学期からは授業の中でのICT機器の活用がさらに広まり、子供たちへの指導に生かされると思います。ご指導をいただいた、情報教育研究調査員の先生方、ありがとうございました。
日 時 7月31日(木)
講 師 上越教育大学 教職大学院 教授 瀬戸 健 先生
演 題 「よい授業が、子どもたちの学び合う学級をつくる」

講師 上越教育大学 瀬戸健 先生

学力向上プログラム研修会
朝日町では、教員としての指導力を養い、資質の向上を図ることをねらいとして、毎年「朝日町とやま型学力向上プログラム研修会」を開催しています。今年度は、児童生徒が学び合う力を高めるための指導のあり方について、上越教育大学教職大学院教授 瀬戸健先生よりご講演をいただきました。
参加した先生方は、子供たちが学び合う学級をつくるために、教師は子供たちとどのように関わればよいか、また、一人一人の子供の学ぶ力を育てるために、教師はどのように指導することが重要かを示唆いただきました。
参加した先生方からは、「『子供に求めたときこそ、教師もいっしょにやってみる』という瀬戸先生のお話から、学級つくりのスタート地点に戻り、児童生徒理解を大切にしていきたい。」「ある子供が、教師の声がけや友達との会話をきっかけに、自信をもって他の子供に話し出す授業のVTRが印象的でした。しっかり子供たちと関わり、魅力ある授業づくりをしていきたい。」など、大きな感銘を受けた感想が多くありました。瀬戸先生、ご指導をいただき、ありがとうございました。
日 時 7月29日(火)
講 師 朝日町立さみさと小学校 教諭 兵庫 秀典 先生
テーマ 1生きる力を育む授業づくり 2プロジェクト・アドベンチャー

授業力アップ研修会

プロジェクト・アドベンチャー
さみさと小学校の兵庫先生を講師に迎え、授業力アップ研修会を行いました。研修では、学級づくりのために、子供たちのよりよいコミュニケーションをつくるエクササイズを指導していただきました。参加された先生方からは、「ホワイトボードを使うことで、自分の思いを簡単に伝えることができました」「オープンクエスチョンやあいづちを通して会話を交わすことで、相手を理解する、自分のことを理解してもらっているという気持ちになりました」「実際にやってみることで、そのプログラムのよさを分かることがでみました。人間関係がうまくいっていると授業でも子供たちは深くかかわれるのだなと思いました」という感想をいただきました。
エクササイズの指導を通して、兵庫先生は、ことあるごとに、子供たちに「よい雰囲気をつくります」「よい仲間意識ができます」「達成感をもたせられます」とおっしゃっておられ、学級づくり、人間関係づくりへの熱意が伝わってきました。兵庫先生、ご指導をいただき、ありがとうございました。