生活科の自然を生かした遊びや自然観察の指導のポイントについて、理科の自然観察の視点や方法について学ぶ、生活科・理科自然観察現地学習会をやまざき紅悠館周辺の自然散策コースで行いました。

生活科理科自然観察現地学習会(秋編)
講師の先生には、カタバミやセンリョウなどの観察を通して、見る、匂いをかぐ、味わってみる、耳を澄ませる、手で触るなど五感を働かせて自然に親しむことが大切であること、秋の草木の特徴や春と秋の草木の様子の違いを理解するなど、教師自身が自然についての感覚を磨いておくことなどを示唆いただきました。
さらに、ノイバラやススキ、トチノキ、クズのつるなど、秋の草木を生かした遊びやリースの工作等も指導していただきました。
これらのことを生かして、子供たちが自然の事物・現象について実感を伴って理解し、自然への愛着を深めることができる授業づくりを考えていきたいと思います。
また、講師の先生には、この研修会のために、コナラやクヌギ、ガマズミ、クサギなど、たくさんの秋の草木や実を準備していただいております。参加者は、自然散策で指導していただいたことと併せて、秋の草木について理解を深めることができました。深く感謝申し上げます。




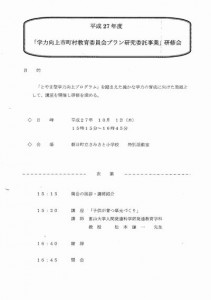 この研修会では、「子供が育つ単元づくり」というテーマで、ご講話をいただきました。
この研修会では、「子供が育つ単元づくり」というテーマで、ご講話をいただきました。
