なんと第50回なんです。
夏休み中の児童生徒の作品の中から優れた作品を一同に展示する「児童生徒作品展」が始まります。先ほど準備と審査を終えました。夏の傑作がいっぱいでしたよ。ぜひご覧ください。
◎日時 平成24年9月22日(土)~23日(日) 10:00~17:00
◎会場 アゼリア ロビーにて
☆第50回朝日町児童生徒作品展出品目録 ← こちらからご覧になれます。
なんと第50回なんです。
夏休み中の児童生徒の作品の中から優れた作品を一同に展示する「児童生徒作品展」が始まります。先ほど準備と審査を終えました。夏の傑作がいっぱいでしたよ。ぜひご覧ください。
◎日時 平成24年9月22日(土)~23日(日) 10:00~17:00
◎会場 アゼリア ロビーにて
☆第50回朝日町児童生徒作品展出品目録 ← こちらからご覧になれます。
この2日間、町内の4つの全ての保育所を廻らせていただきました。新しい建物も古い建物もあり、大人数と小人数もあり、それぞれにいいところがあるもんだなと思いました。まだまだ暑いのですが、園児たちはとっても元気に運動会の練習をしています。しばらくしか見ていないのですが、保育所の先生の言葉がけの巧みさにただただ感心しました。
一度も観たことがなかったのです。今回、少し観にいけました。
以前から小学校の校長先生が「行進など、本当に素晴らしい。普通は、小学生の方が元気で上手なのだが、朝日中学はすごい。小学校も負けてられないね。」とよくおっしゃっていました。
さすがですね。1年生も、すっかり朝日中の文化を継承しています。行進では、軽く握った手が肩まで上がるのですから、もちろん女子も含めて全員です。前に立って挨拶される方の会釈には、全員の首が深く折れます。さて、応援披露だけのぞきに行ってきました。運動会は、やっぱり「応援」でしょう。
やるなあ。のびのびと、でもアイディアがあって、しっかりと揃っています。 相当、必死になって取り組まないと、ここまではできない。お見事です。普段見る、よく挨拶してくれる中学生たちの、またひとつ違ったチカラをみせてもらい、少し元気になりました。



「道徳のチカラ代表」の佐藤幸司先生が富山に来てくださいました。朝日町教育センター主管ですので、これが一番の楽しみであり、終わるまではセンターが落ち着かない事業です。
昨晩、1991年の「道徳授業研究」を引っ張り出してみると、そこには20代の佐藤幸司先生の論文と実践が載っているのです。「あっ、この実践真似した」ということを思い出しました。世は法則化時代で、なんとか授業ができるようになりたいと日本中の若い教師が熱かった時代でした。そのときの代表だった深澤先生が退職され、若者だった佐藤先生が50代になっておられます。いつまでもお若く見えます。
講演の内容は、さすがです。講座には一抹の不安もありませんでした。皆さんが満足されたり、少し前向きな気持ちで授業に向かうエネルギーになることは予想とおりです。それほどの先生なのです。
どちらかというと、「つまらない」と子どもが感じていることの多いのが道徳ではないでしょうか。 本当はそうではなく、週に1時間がとても大事ということがよくわかりました。書籍がたいへんたくさん売れました。ということは、講演がすばらしかったのです。
朝日町教育センター関係の夏の研修は、今日で終わりました。たくさんありました。先生方、お疲れ様でした。さあ、2学期ですね。





●友好都市である「釜石市」の訪問団が帰朝し、防災教育に役立てて欲しいと、たくさんの書籍とDVDをいただきました。
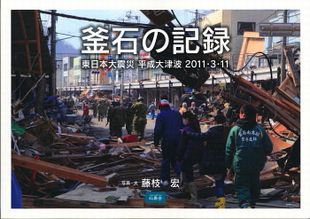
→詳しくは、↑ の図書・DVDをご覧ください。 【8/21】
●「その時歴史が動いた」DVDが入りました ↑ の図書・DVDをご覧ください。 【8/18】
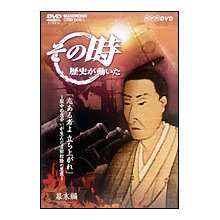
元KNBアナウンサーでディレクター。入善町在住。現在は、「細川嘉六ふるさと研究会」の代表である金澤敏子氏をお招きして、学校教育運営研修会の2回目が行われました。テーマは、『「泊・横浜事件」を取材して』です。朝日町の「紋座」にゆかりの大きな事件であるが、なかなか見えにくかった歴史の陰のところです。朝日町や泊に生まれ育っていてもよく知らないのは、なぜだろうと思っていました。戦後も再審中であったこと、記録が抹消されていたこと、そしてそれを風化させまいとした人たちがいたことを知りました。つくづく、この朝日町というのは実に深く、重い歴史をもった土地だと感じました。



朝日町の教育の特色の一つでしょう。小、中、高校の教員が一緒になって講演を聴くという会があります。県下でも珍しい活動です、朝日町は一町に一中学、一高校ということもあり、生徒指導研修会など小、中、高校の連携が強く意識されています。
さて、講演会は、「放射線の一般知識と人体の影響」と題して、富山大学の鳥養祐二先生をお招きして、行われました。放射線についての基礎的な講演でしたが、ほどよい内容で、わかりやすい講演でした。放射線の一つ「カリウム40」は、干し昆布1kgあたりに2000ベクレルだが、ビールには10ベクレルというお話が心に残りました。



まさに「伏黒劇場!」
一度は聴かなくちゃと言われる 教育記念館 館長 伏黒 昇 先生を講師に朝日町学校教育運営研修会が開催されました。「とやまの至宝:ヘルン文庫」と題したお話は、実はここ朝日町の泊と深くつながったお話なのです。たいへん深い知識とお話の構成、語り口、そして演出とも、至高でした。「今まで聴いた講演の中で最も興味深かったです」という感想が参加者からありました。
次回は、8/17(金)に金沢敏子さんの「泊・横浜事件」についてのお話を聞きます。まさに、今日の続きのような知っているようで知らない朝日町の歴史のお話。
朝日町郷土教育教材研究開発調査員会の企画で、県の総合教育センター科学情報部に講師依頼をし、朝日町の自然分野についての現地研修をしました。例年、歴史的、文化的な分野が多かったので、理科的な視点でのアプローチは珍しいです。今年度から採用6年目までの先生たちは悉皆研修となりました。鹿島樹叢での動植物の観察。そして笹川での水性昆虫の観察でした。暑いわりには、樹叢の中と川に入れたので、なんとか先生たちも耐えられたようです。お疲れ様でした。






